愛知県の知多半島で、寄生虫「エキノコックス」に感染した犬の報告が相次いでいます。国立感染症研究所が”半島内で定着した”との見解を示していますが、定着確認は北海道外では異例のことです。愛知県は”まん延している状況ではない”としていますが、これからの動向が注目されています。今回はエキノコックスとは何なのか?感染したら身体にどのような影響があるのか解説していきます。
感染したらどうなるのか?
もともとエキノコックスは北海道で多くの感染例が報告されています。キタキツネからきているという説が有力ですが、犬の感染も多く、それらの”ふん”などに含まれる卵が人体に入ることで影響を及ぼします。人体に入ったエキノコックスは幼虫となり、10年ほどたってから肝機能障害などを引き起こします。
どこから感染するのか?
愛知県感染症対策課によると、狂犬病対策で捕獲した野犬の調査で見つかっており、いずれも感染経路は不明ということです。
一般的にエキノコックスは”ネズミ”などが中間宿主になり、幼虫を持つネズミを”野犬”や”キツネ”が食べることで広がると言われています。
| 【卵】 ⇒卵がついた木の実などを野ネズミが食べると、肝臓のなかで幼虫になる |
| 【幼虫】⇒幼虫が寄生している野ネズミをキツネが食べると、キツネの腸で成虫になる |
【成虫】⇒腸の中で卵をつくり、フンと一緒に排出 |
人への感染
人から人に感染したり、野ネズミから人に感染することはありません。人間が感染する経路としては、エキノコックスの卵に汚染された山菜や沢水などを直接口にしたり、卵が付着した手指を介して感染して、野ネズミと同様にエキノコックスの幼虫が肝臓に寄生します。エキノコックスの卵は、直径0.03mmの球体で肉眼では見えませんが、十分な加熱や水洗い(手洗い)で、感染を予防することができます。
自覚症状
エキノコックスに感染したとしても、すぐには自覚症状が現れません。数年から10数年の潜伏期を経て、上腹部の不快感や膨満感が現れ、しだいに肝機能障害に伴うだるさや黄疸等の症状が現れ、放っておくと肺や脳に病巣が転移したり、命にかかわることもあります。
治療
もしも感染してしまったら、だんだん悪化して命にかかわることになりますので、すぐに治療が必要になります。どんな病にも言えることですが、エキノコックスも早期に発見して早期に治療することが大切です。治療方法は「薬物治療」もありますが、根治するためには「外科手術」で病巣を切除します。
予防
- 野生動物のえさになる残飯や生ごみを放置しない
※人間の身近に近寄らせない! - 沢水や小川の生水は飲まない
※万が一、卵が混入していると重大な感染源に! - 野山の果実や山菜を食べる場合には、水道の水で
よく洗うか、十分熱を加えてから食べる
※100℃では1分以上、70℃では5分以上。 - 犬の放し飼いはしない
※キツネや野犬との接触を避ける。
※散歩中に拾い食いをさせない。
※フンの始末は速やかに! - 野山に出かけたらしっかり手洗いをする

犬が感染すると、フンと
ともに卵を排泄するので
人間への感染源になって
しまいます。
まとめ
エキノコックス症は、エキノコックスという名前の寄生虫が主に肝臓に寄生しておこる病気で、道内では毎年10数名の患者が見つかっています。道外ではあまりみられない病気でしたが、近年愛知県の知多半島で報告が相次ぎ、定着しました。感染経路は不明なところが多く、今後どこで発生するかわかりません。だからこそ予防対策をしっかりとしていく必要があります。特に家で犬を飼っているご家庭や、小さな子どもがいて良く公園で砂遊びをしているというご家庭は注意してみてあげてください。
また⇨【迷ったら買うべき非常食】では、もしものために備えておきたい、オススメの非常食を紹介しています。保存方法や上手な備蓄方法も合わせて紹介していますので、まだ用意していない方はリストアップしながら、すでに用意されている方は準備し忘れがないか参考にしてみてください。
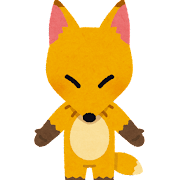


コメント